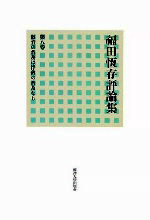
福田恒存という思想家は「偉大なる常識家」である。
したがって常識が通用しない時代に重宝されたのは当然だったにしても、ますます常識を失った現代日本において、ますます貴重な存在として輝き続けるのである。ちょうど評者(宮崎)は学生時代だった。
本書に収められた評論の数々(ほぼすべての論文が昭和四十年から四十五年)を私は当時、夢中で読んだ記憶がある。学生運動真っ盛りの頃である。
慶応、早稲田に端を発した大学紛争は、暴力的になって日夜激化し、昭和四十五年に赤軍派ハイジャックと三島事件へといたる。日本が騒然としていた。
大学は荒廃し、教育が歪曲され、価値紊乱が方々で起きていた。福田は常識の回復を訴えていた。
夢中で読んで、福田氏に講演に来てもらったことも数度。電話での長話も経験した。最初に講演を依頼したのは昭和四十二年だった。「戦後日本の知的退廃」とかの演題だった。
感動したのは学生新聞の編集者風情を一個の大人として扱ってくれたことだった。
このたび福田恒存評論集に改められると、私はどうしてもあの時代の感傷にまず浸ってしまう。左翼学生運動も論争も激動だった時代が、つい昨日のように脳裏に蘇るからである。
たとえば昭和四十四年の『諸君!』創刊号に福田氏は次のように書いた。
「大方の日本人は大東亜戦争の敗北によって『醜の御楯(しこのみたて)』としての生ける目標を失った。が、それを失うより早く手に入れた生き甲斐は戦争犯罪に対する懺悔の心であり、贖罪意識である。(中略)生き甲斐のごとき本質的な事柄において日本人の関心を引くのは、つねに心懸けであって行為ではなく、意であって形ではない」
「必要なのは心の拠り所であり、それはすべて平和憲法に預けた格好になった。これは二重の皮肉である。第一に罪悪感という消極的な概念に生き甲斐を求めた事であり、第二にそれを積極的に誇りに転用したことである」(本評論集304p)。
『平和憲法』なるものを後生大事な経典とした知識人は偽者だと皮肉っているのである。
また福田恒存氏氏はこうも書かれた。
「私はこの平和という名の武器の威力を信じます。隋って平和主義や中立主義を非現実的な観念論となし、その不可能を説く私を目して現実主義を言うのは当たらない。なるほど私も平和主義や中立主義の非現実性を非難して参りました。しかし、それが実際に非現実的で無効化ならば、わざわざ反対する必要はない」(中略)
「平和という名の美しい花を咲かせた日本の薔薇造りは、そのヒューマニズムという根がいつの間にかエゴイズムという蟲にやられている事に、果たして気づいているかどうか。そのけちくさい、ちっぽけな個人的エゴイズムに目をふさぎ、今度は同じヒューマニズムの台木にナショナリズムを接木して、平和と二種咲き分けの妙技を発揮しようとしている」
「ナショナリズムを口にする者が本当に日本民族の自覚を持っているのか」(中略)「ヴェトナムの民族主義を理解し得る様な口吻を進歩的知識人の言動に感じるとき、私は文字通り呆れ返ってものが言えなくなる」(初出は読売新聞、昭和四十年六月八日。本評論集、132p-133p)。
「べ平連」なる似非知識人と付和雷同の学生らの団体が結成される直前に、はやくも似非平和主義の方向を予知し、批判しているのだ。
昭和四十年代初頭、論壇は左傾化が激しかったが、その分、保守派文化人も『自由』や『文藝春秋』で健筆を振るっていた。『諸君』も『正論』も『ボイス』も創刊されていなかった。『サピオ』も『月刊日本』も、『WILL』もなかった。思想界では一方に林房雄、保田與重郎がいた。岡潔がいた。林の『大東亜戦争肯定論』は民族派のバイブルだった。三島由紀夫が『英霊の声』、『喜びの琴』などを書いて保守陣営に飛び込んできたのも、この時代だった。いきなり福田の大常識を飛び越えた保守論壇に加わってきたのだ。
体制派御用の論客には猪木正道がいて、高坂正尭が登場したばかりだった。永井陽之助がデビューしてきた。
保守の伝統的な論客らはミニコミ誌で活躍していた。竹山道雄や会田雄次が大車輪の活躍をする直前であった。福田は保守論壇のチャンピオンとして、その発言が逐一注目されていた。
「正気の狂気」が三島なら、福田は「狷介孤高」の士
『論語』によれば、知識人には「狂」と「狷」がある。
「子路第十三」に「子曰く 中行を得て之に与せずんば、必ずや狂狷か。狂者は進みて取り、狷者は為さざる所有るなり」。
「狷介孤高」の士とは仕事がなかなかしにくく、狂の人は他人がしないことを率先して突っ走るという意味である。要は行動するか、評論に徹するか。
山県有朋は青年時代を「狂介」と号した。陸奥宗光の号は「六石狂夫」である。
吉田松陰も西郷隆盛も、そして三島由紀夫も「狂」の部類であろう。
「狷者」なら岡潔も、板垣退助もそうだろう。そして、私は福田恒存を「狷」のほうに分類してしまう。
三島事件が起きたときに林房雄は「正気の狂気」と比喩して三島の行為を分析した。
「狷」のほうの福田は「わからない。わからない。私には永遠にわからない」という名文句を吐いて、以後、三島事件に関する論評を一切行わずに沈黙した。かわりに江藤淳が猪口才なことを言い募ったが、小林秀雄に叱責されたものだった。
福田恒存の評論集は、一度文藝春秋から出た。昨年から全十二巻の新装版として、麗澤大学出版会から刊行が始まった。その第一巻は教育論、国語論、祝祭日、憲法論などが選ばれているが、最後に珍しく「乃木将軍と旅順攻略戦」が挿入されている。
乃木将軍を無能と断じた司馬遼太郎への鋭角的批判であり、これを書かれたのが三島事件直前であったことも何かを象徴している。司馬の“乱世史観”なる似非歴史分析を透視して、『合鍵を持った歴史観』と木っ端微塵に打ちのめした。
いずれの文章も想い出が深く、あの時代と自然に重複してしまう。
|